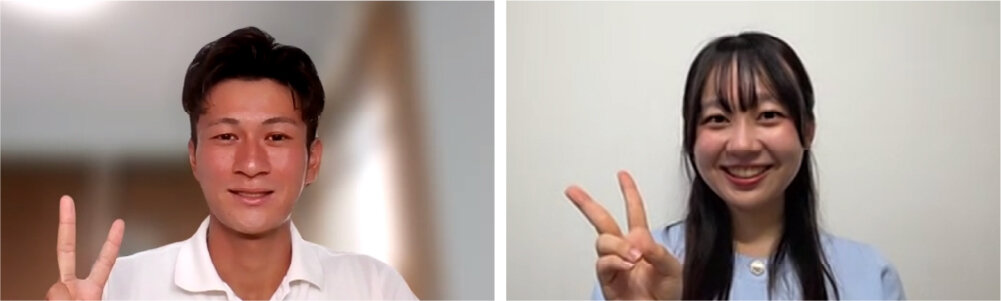このインターンシップが一歩踏み出す勇気をくれた。
-
R.O. 神戸大学 国際人間科学部

-
H.K. 早稲田大学 文化構想学部

夢を描き、周囲を巻き込む仕事。
社員と対話することで迷いや不安が消えた。
日鉄興和不動産へ入社を決めた
理由を教えてください。
-
R.O.
最後の決め手は、やっぱり「一緒に働く人」だったなと。最初にデベロッパーに憧れた理由は、決められる物事の大きさでした。でも、いざデベロッパーで働くことが現実味を帯びてくると「本当に自分にできるのか?」と一瞬ひるんでしまったんです。そんなときにインターンシップに参加したら、日鉄興和不動産は先輩社員や人事の方が本当に優しくて。わからないことは全部教えてくださり、真剣に向き合ってくださいました。社員さんとのコミュニケーションを通して「この会社だったら、責任感ある仕事もやり遂げられそうだ」と安心できたんです。
-
H.K.
私もR.O.さんと同じで、詰まるところは「人」ですね。デベロッパーの仕事を知れば知るほど「街をつくりたいという夢を描くだけでは無理なのかもしれない」という考えが募り、一度デベロッパー業界をあきらめた時期があったんです。それでも日鉄興和不動産は雰囲気が良くて、夏と冬のインターンシップに参加しました。社員の皆さんは個性豊かなのですが、お仕事への熱量は共通していて。「この人たちと働きたい」と心から思える会社でしたね。デベロッパー業界で働く不安を払拭してくれたのも、社員さんの言葉です。「街づくりには夢がないといけない。デベロッパーは夢を示すことでいろんな人を巻き込んでいくんだよ」と。数々の修羅場を潜り抜けてきた人が、そう語ってくれる会社なら、辛いことも一緒に乗り越えていける気がしました。
デベロッパーに興味を持った
きっかけを教えてください。
-
R.O.
飲食店の配達のアルバイトをしていたときに、マンションによって共用部の造りが全然違うことに気が付いたんです。何もない空間もあれば、夕方になると主婦や子どもたちが自然に集まり、温かい雰囲気に包まれている共用部もあって。そうした違いを目の当たりにして、どういう会社が造っているのか調べていくうちに、デベロッパーの存在を知りました。最初は業界を絞らず幅広い会社を見ていたのですが、それ以降の就職活動はデベロッパー業界に絞り込みました。
-
H.K.
私は高校生のときから街づくりに興味があり、大学では町内会や地域コミュニティといったソフト面の街づくりを研究していました。この研究を仕事につなげられないかと考えたとき、最初に浮かんだのがデベロッパーだったんです。ゼネコンや街づくりコンサルなども見ましたが、ゼネコンはハード面に特化していますし、街づくりコンサルは事業主ではないですし。ソフトとハードを合わせて、自らが主体となり総合的な観点から街づくりを進められるのは、デベロッパーの特権だと感じました。
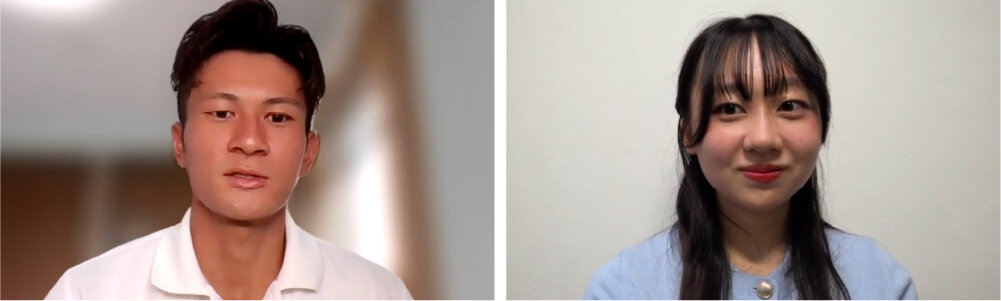
称賛だけじゃない。
本質を突く問いが、私の視野を広げてくれた。
Day1-2(就業体験)では
どのような仕事を体験しましたか?
-
R.O.
事業開発本部の用地部に配属されました。ホテルやオフィスの用地を仕入れる部署です。1日目は実際に仕入れた用地に建てられたオフィスビルを見学し、先輩社員から土地を購入するまでのストーリーを聞きながら、周辺の街を歩きました。2日目は最近購入した土地を見に行って、その土地での開発プランを提案するワークに取り組みました。採算性、街の人が求めていること、自分がやりたいことのバランスをとるのが難しかったですね。でもそれ以上に、ゼロから自分で考え、決められることがとても楽しかったです。
-
H.K.
私は開発企画本部の開発営業グループで、大規模再開発事業のお仕事を体験しました。1日目は3つの会議に出席し、たくさんの専門用語が飛び交うなか、泥臭い調整をされている姿を目の当たりにしました。社員の方々の熱量を知り、デベロッパーをあきらめかけていた気持ちが「この会社すごい素敵」と傾いたのを覚えています。2日目は仕込み段階の再開発プロジェクトを題材にして、その開発コンセプトを企画するワークをおこないました。街の人の声を集めるために、地元小学生が再開発の要望をまとめてくれた展示などを参考にしながら、アイディアを具体化させていきました。
インターン中に出会った
部署の人たちからは
どんなフィードバックがありましたか?
-
R.O.
部長も含めてグループ全員が集まった環境で、ワークの発表をさせていただきました。インバウンド向けのホテルの提案をしたところ、部長からは「日本人の利用客はどうするの?大事な視点が抜けているよ」と厳しい指摘をいただきまして。半分怒られたような形でしたが、私はそれがとても嬉しかったです。他社のインターンでは「すごいね」と肯定されて終わることが多かったのですが、この会社では一人の学生に対して本気で向き合ってくれているのが伝わり、そういうところに惹かれましたね。
-
H.K.
私は最終発表の前に、社員さんに相談したところ「もう少し地域の人のことを考えてもいいんじゃない?」というフィードバックをいただきました。その一言が今でも心に残っています。いろいろな会社の社員面談を重ねるうちに「もっと採算性を考えなければ」という考えが先行してしまい、自分が一番大切にしたかった「地域のために」という視点が欠けてしまっていることに気づかされました。「採算性も、地域の人々のことも、両方考える必要があるんだ」と思い出すことができたのは、自分にとって大きな収穫でした。
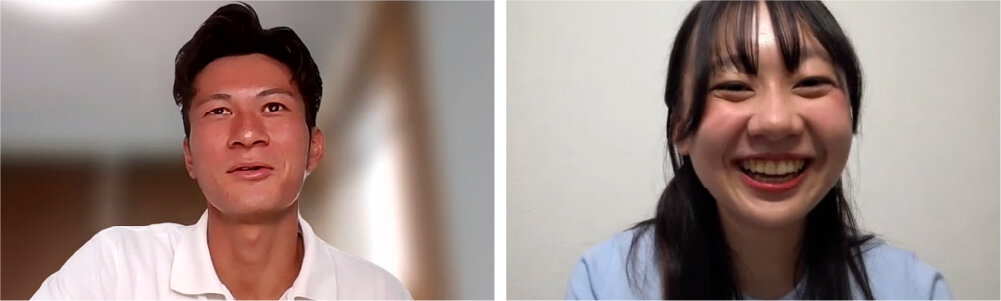
もっと欲張りになっていい。
なりたい社会人像がはっきり見えた。
5Days インターンシップを通して
自分自身にどんな+aがあったと
感じていますか。
-
H.K.
一番大きな変化は、あきらめかけていたデベロッパーにもう一度チャレンジしようと気持ちを切り替えられたことです。街づくりには採算性も大事だし、地権者・地域の想いも大事。どれか一つに絞る必要はなくて、もっと欲張りになっていいんだなと。その欲張りを実現するために、全力で仕事に取り組む社会人になろうと思えたんです。
-
R.O.
私はデベロッパーの仕事を体験して、大きな物事を前に進めていくには推進力が一番必要だと気づかされました。推進力のエネルギーとなるのは、相手が何を求めているのか耳を傾けることと、自分がどうしたいのかを伝えること。人の意見に従うだけではなくて、自分の想いを乗せていくことの大切さを実感しました。
そう思えた出来事は何でしたか?
-
R.O.
DAY3のグループワークですね。用地・開発・営業の担当に分かれて開発プランを決めていく過程で、担当者同士で意見が対立することも多くて。相手の意見に従うだけ、自分のやりたいことを伝えるだけでは、上手くいかなかったんです。この気づきは学生生活にも活かされています。今、大学で土のグラウンドを人工芝に変える数億円規模のプロジェクトに関わっています。金額が大きいため、OBOGや大学職員を巻き込んでいかなければなりません。自分の想いをしっかり伝えながら、何とか前に進めようと奮闘中です。
-
H.K.
私はDAY5に取り組んだワークの影響が大きかったですね。日鉄興和不動産が掲げる街づくりのコンセプト「人と向き合い、街をつくる」をテーマに、どうやったら人と向き合えるのかをチームで話し合うという内容でした。私たちのチームが議論を重ねた末に導き出した結論は、端的に言えば「究極の人好き」。それが自分のなかですっと納得できて、なりたい社会人像にぴたりと重なりました。
学生時代に力を入れたことを
教えてください。
-
R.O.
サッカー部の広報部長として、チームのスポンサー獲得に奔走しました。私たちのチームは強豪校とは違い、サッカーの成績でスポンサーを獲得するのは難しかったので、地域貢献やSNSでチームの魅力を伝えることに注力しました。こども食堂にお手伝いに行ったり川の清掃をしたり防災イベントに参加したり、とにかく地域のボランティアに積極的に参加していましたね。ただ、週6日でサッカーの練習があるため、忙しい部員たちにボランティア参加を促すのは簡単ではなかったです。スポンサー獲得の具体的なメリットを示しながら、一生懸命説得しました。
-
H.K.
私は雑誌制作サークルのライター部門で活動していました。私自身はライター業がとても楽しく充実していたのですが、一方で新入生がすぐに辞めてしまう状況に危機感を抱いていました。その背景にあったのは、雑誌制作とは何かが伝わっていないことと、部員同士の接点の少なさでした。そこで他部門と連携し、新入生向けに雑誌制作体験プログラムを企画しました。先輩部員にインタビューしてもらって、それを誌面化することで、先輩部員との接点の創出と雑誌制作体験を両立させました。
将来、日鉄興和不動産で
どんな仕事をしたいと
考えていますか。
-
H.K.
キャリアのどこかのタイミングで、大規模再開発に関わりたいですね。いろんな人の想いに触れながら、一つの建物を形にし、そこに人が集まる…そんなプロジェクトを主導する立場になれたらと思っています。それを実現するためには、人から信頼され自然と周囲を巻き込めるような、人徳のある社会人になるのが目標です。大規模再開発は、人の想いを聞くことから始まるお仕事だと思っていて。そういう点が、学生時代から取り組んでいるライターの活動にも通じるものがあり、自然と惹かれるんですよね。
-
R.O.
デベロッパーに興味を持ったのはマンションがきっかけでしたが、インターンシップ後はオフィスやホテルなど幅広い分野に興味が湧いています。ただ、いずれも大きい金額が動く事業なので「この人に任せたい」と思ってもらえる仕事をしたいです。インターンシップで3年目の社員さんとお話をしたときに「自分がこの土地を買ったんだよ」と教えてくださって。若手社員の方も社内外から信頼され、活躍されている様子にとても刺激を受けましたね。私も入社後は先輩方からたくさんのことを学び、早く信頼される存在になりたいです。