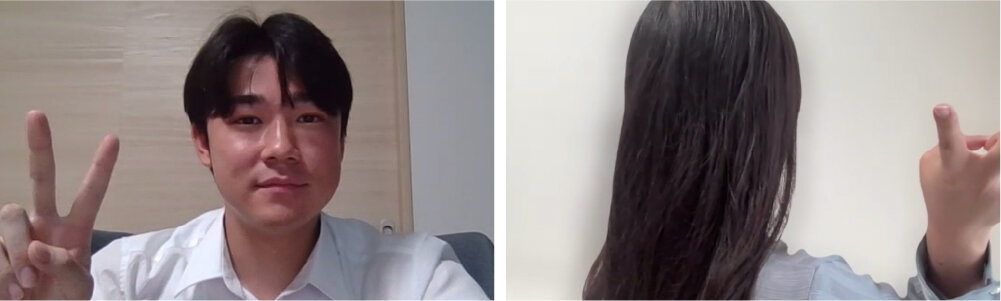一人ひとりの働き方を間近で見て、仕事の解像度が上がった。
-
Y.O. 関西学院大学 国際学部

-
M.K. 東京大学 経済学部

直感を頼りに就活をスタート。
デベロッパーという選択が、確信に変わるまで。
就職活動を始めたのは
いつ頃でしたか?
-
M.K.
大学3年生の5月〜6月頃です。ちょうど夏のインターンシップの選考が始まるタイミングでした。初期の頃はとにかく“ミーハー就活”という感じで、デベロッパー業界に限らずエンタメや広告など、自分が直感的にワクワクできる企業を中心に応募していました。
-
Y.O.
私も3年生の6月頃から始めた気がします。すでに就職活動を終えた友人から「夏のインターンシップは絶対行ったほうが良いよ」と言われ、「そうなんだ、じゃあ出してみよう」という流れで。最初はまだ業界の理解が深まっていなかったので、私もM.K.さんと同じ“ミーハー就活”のようなスタイルで、興味のある企業に幅広くエントリーしていましたね。
デベロッパー業界に
興味を持ったきっかけは何ですか?
-
M.K.
夏に他社デベロッパーのインターンシップに参加し、事業のスケール感や、仕事を通して面白いことを仕掛けられる可能性に惹かれ、興味を持つようになりました。最終的には広告会社とデベロッパーから内定をいただきましたが、事業主として主体的にプロジェクトを進められる点に魅力を感じ、デベロッパーを選びました。
-
Y.O.
私はオーストラリアで建築作業員として働いた経験や、世界各国を旅するなかで、街の成り立ちや文化との関係性に触れ、建築への興味が芽生えました。そのときはデベロッパーの存在を知らず、ゼネコンを中心に応募していたんです。そんななか、ゼネコンだと思って応募したのが実はデベロッパーのインターンシップで。そこで初めてデベロッパーという仕事を知り、冬以降はデベロッパー業界に軸足を移しました。
どんな考えを持って
就職活動を進めていましたか?
-
M.K.
私が見失わないようにしていたのは「自分がずっと楽しんで取り組める仕事かどうか」という点です。日鉄興和不動産については、志望動機を考えたり社員さんと会話したりするときに、「私だったらこうしたい」という気持ちが次々に湧き上がってくる感覚があって。「嘘じゃなく本当にやりたい」と心から言える会社だったんです。
-
Y.O.
私は「大企業にしかできない、スケールの大きな事業をやってみたい」という考えを持って就職活動をしていました。たとえば億単位で土地を買い、そこに建てた建物に1日数万人の人が訪れるようなプロジェクト。こういった事業は個人ではなかなか実現できないことだと思い、大企業ならではのスケール感に憧れました。
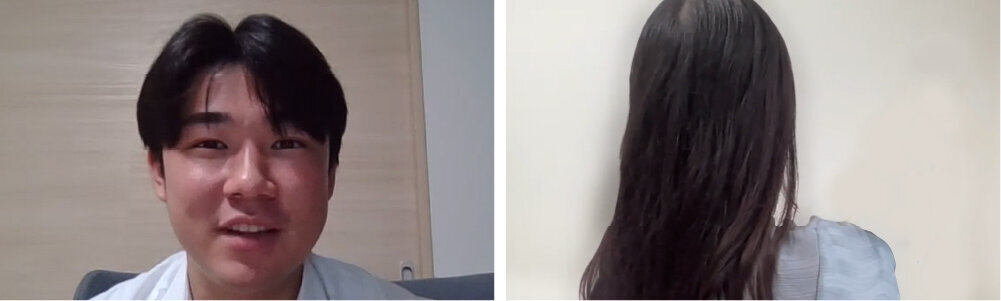
ゲーム形式のワークで、仲間とバトンをつなぐ。
再開発の流れを疑似体験。
DAY3 「デベロッパービジネス
体感ゲーム」で感じたこと、
得られたものについて教えてください。
-
Y.O.
1グループ6名で、用地・開発・営業の担当に分かれて、再開発事業に取り組むゲーム形式のグループワークでした。用地取得から開発、営業へとバトンをつなぐ一連の流れを体験でき、デベロッパー業務の全体像をつかむ貴重な機会になりました。
-
M.K.
ゲームの仕組みそのものが、新鮮だったよね。他社のインターンでは既定の土地をもとに開発プランを考えるグループワークが多かったのですが、今回は用地取得からリーシングまで、すべてのフェーズを体感できるのがすごく面白かったです。サイコロで結果が左右される”時の運”の要素も斬新で、もし望ましくない結果が出ても、どうリカバーするか皆で話し合うプロセスが、実際の業務に近いと感じました。
二人はどのフェーズを
担当したのですか?
-
Y.O.
私は用地担当です。用地担当が取得した土地の面積によって、その後の開発でできることは大きく変わります。グループのメンバーとは初対面だったので、空気を読みながらも、できるだけ広い用地を獲得する必要があり、サイコロを振る瞬間はかなりのプレッシャーでしたね。
-
M.K.
私は開発を担当しました。容積率を確保するための行政協議や、ゼネコン選定などが主な業務です。ゲーム上ではサイコロを転がすだけなので、苦労は全くありませんでしたが、実務では大きな責任が伴うだろうと想像しました。「何としてでもやり遂げなくては」という覚悟が求められる仕事だと思います。
Day1-2では、
どんな就業体験をしたか
振り返っていただけますか?
-
M.K.
事業開発本部で、大規模なオフィスを開発するお仕事を体験しました。ミーティングに出席したり、社員さんが担当している物件の周辺を一緒に歩いたりして、現場の空気を肌で感じることができました。そのとき、今でも忘れられない出来事がありまして。街を歩いている途中、社員さんが突然走り出したんです。「見たことのない工事現場だ、ちょっと見に行きたいから先に行くね」と。走っていく背中を見て、本当に好きでこの仕事をしていることが伝わりましたし、自分の仕事を突き詰める探求心がすごいなと思いましたね。
-
Y.O.
私が現場配属で体験したのは、住宅の用地取得のお仕事です。社員さんと一緒に、購入したばかりの土地の現地調査に行ったのですが「一丁目はこういう特徴があって、二丁目はこうで…」「ここは再開発の影響で地価がこれだけ上がっていて…」と、区画ごとに細かく解説してくださって。その知識量に圧倒されましたし、語っている姿もすごく活き活きしていて、楽しそうに仕事をしているのが伝わってきました。社員さんは「用地を買わないと開発できない。皆の食い扶持を稼ぐ覚悟で仕事をしている」とおっしゃっていて、会社の根幹を担っているプライドが感じられ、とてもかっこよかったです。
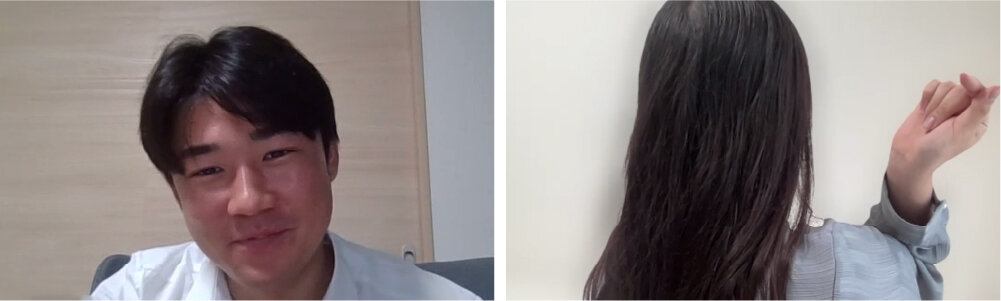
華やかさだけじゃない。
地道な積み重ねがダイナミックな街をつくる。
インターン中に出会った先輩社員の
働き方の面などで
印象に残ったことはありますか?
-
Y.O.
就業体験を通じて、社員さんがコミュニケーションを大事にされている印象を受けました。「千三つ」という言葉があり、その意味は1000件の土地情報があるなかで検討に値するのは、ほんの3件程度ということ。だからこそ信頼関係を築いて「あなたになら紹介してもいい」と思ってもらえるような丁寧なコミュニケーションが欠かせないのだと思います。実際の打合せでも、業務の話だけでなく、家族やゴルフの話も交えながら、和やかな雰囲気を作っていました。そうした日々の積み重ねが、良質な土地情報の取得につながっているんですね。
-
M.K.
私は、就業体験を担当してくださった社員さんの働き方が特に印象的でした。その社員さんは北海道に赴任されているときに、開発業務に取り組みながら、不動産鑑定士の資格を取得されているんです。すごく向上心があるというか、自分の仕事に熱意があるのが伝わりました。私もそのくらい情熱を持って自分の仕事に向き合いたいですし、そうした方々が集まっている職場であれば、きっと良い影響を受けながら成長できると思います。
インターンで仕事を体験するなかで、
どんな収穫がありましたか?
-
Y.O.
大きい建物の裏側にある“ダイナミックさ”を肌で感じられたことが、何よりの収穫です。「普段何気なく利用している商業施設などの建物は、これほど多くの人が関わり、莫大な資金が動き、何度も議論を重ねてようやく形になるものなんだ」と。目や耳から得る情報以上に、現場の空気から体感として伝わってきました。大規模な建物が建つことで、人の動線や周辺住民の暮らしが変わるため、とても責任の重い仕事です。日鉄興和不動産の方々はそうした影響にも配慮しながら、関わるすべての人がプラスに感じられるように努力されていました。
-
M.K.
デベロッパーの仕事や社員さん一人ひとりの業務について、ぐっと解像度が上がりました。たとえば、就業体験でご一緒した社員さんは、現場の裏方業務にも積極的に関わっていました。「数時間前の会議では、すごく大きなことを決めていたのに、こんなことまでするのか」と驚いたのを覚えています。華やかな仕事ばかりではないことは承知していましたが、そういう姿を見てもなお「この仕事がしたい」という気持ちは揺らがず、自分の想いを再確認できました。
最後に、就職活動を振り返って
一言お願いします。
-
Y.O.
振り返って感じるのは、「就職活動は自分の人生を評価される場ではない」ということです。何より楽しむことが大切だと思います。企業の方々が自分に興味を持って話しかけてくれることや、今まで知らなかった企業が実は社会に大きく貢献しているのを知れたことは、純粋に楽しい経験でした。就職活動をスポーツに例えて、勝ち負けにこだわる人がいますが、私はそうは思いません。選考結果に一喜一憂するよりも、自分自身の納得感を大切にしたほうが、メンタルも安定するはずです。
-
M.K.
面接に臨むときは、良い意味での図太さが必要だと思います。これは自分自身の反省から言えることなのですが、「どうしても入社したい」「この企業が大好き」という気持ちが前面に出すぎると、かえって上手くいかないことがありました。熱意が強すぎるあまり、自分の話ばかりしてしまい、相手と対話が成立していなかったんですよね。逆に、肩の力を抜いて図太く臨んだ企業は、選考を通過することが多かったんです。やはり冷静さと余裕を持ったマインドセットが大事だと実感しました。